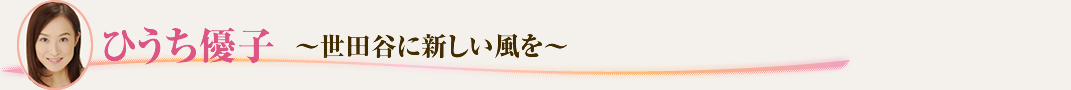
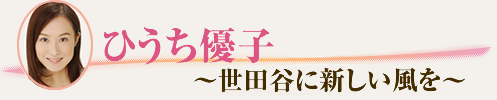
【その他】記事一覧
◎公園へのドッグランの整備について
課題
・2022年に発表されたデータによると、日本で飼われている犬は約705万頭。
・新規に飼育される頭数はここ数年減少傾向だが、依然として人気は高く、住宅都市である世田谷においては、かなり多くの方が犬をはじめ、ペットを飼っている。
・私のところに、以前から「世田谷区内にはドッグランが少ない、公園などにドッグランを増やしてほしい。」との声をいただく。
課題解決に向けた質問・提案
世田谷区内に、ドッグランが少ない、増やして欲しい、という声をいただく。
犬が遊べる広さを確保できる場所は、公園内と考える。新たに公園内にドッグランを整備していただきたいと考えるが、区の見解を伺う。
成果
・世田谷区内の公園内のドッグランの設置状況は、都立駒沢オリンピック公園、蘆花恒春園の2か所。
・区立公園においてはこれまで常設のドッグランはなく、区民団体である野川ドッグエリアの会が運営主体となり、月数回実施されるドッグエリアが1か所ある。
・区立公園は都立公園ほどの敷地がなく、隣接する住宅までの距離が近いことなどから常設のドッグランを設置することは極めて難しい。
・公園における犬に関する課題は、ふんの放置、ノーリードや犬を制御できないような伸縮式リードの使用、犬の鳴き声など様々ある。
・公園等の一部を犬専用として使うためには、現状の犬に対する考えが区民の間で相反する状況を改善させる必要がある。そのためにも、犬に関わる人たち自身が主体となって継続的なしつけ教室などに取り組み、マナーが向上し、公園利用者や近隣住民などの理解を得ていくことが求められる。
・今後、犬と暮らす方々の公園の利用改善を目指し、引き続き、野川ドッグエリアの会を支援するとともに、新たにドッグエリアの運営を担う意欲のある団体などが現れた際は、世田谷保健所などと連携し、区の取組を説明し、協議することから始める。
◎環境に配慮したESG債の購入について
課題
・世田谷区はふるさと納税で、税収が減っている。税外収入の確保が必要。
世田谷区の運用の現状
超低金利時代の中でも積立基金を債券などで運用して年間2億円を超える利子収入を上げている。
課題解決に向けた質問・提案
・気候非常事態宣言をし、2050年までにCO2削減実質ゼロを表明した世田谷区は、今後、債券を購入する際、環境に配慮したESG債の購入についても検討することを、以前に提案した。
・その結果、早速、令和4年度の公金運用計画には、ESG債については、安全性、流動性、効率性を考慮した上で購入を検討すると明記された。
・ESG債は17年度に東京都が初めて環境債を発行したが、近年、環境問題への関心の高まりを受けて各地方自治体がESG債を発行する動きが広がっており、令和4年5月に滋賀県が発行したESG債には発行額の10倍近い購入希望があった。
・各自治体が発行するESG債は、世田谷区が購入する際の基準の一つである安全性も高いと思われ流ので、他の債券と比べて利率が同程度であれば、ぜひ購入して利子収入を確保するとともに、環境問題に積極的に取り組んでいる世田谷区をアピールすべきと考える。
・区の今年度のESG債購入実績と来年度の予定について伺う。
成果
・SDGsへの関心の高まりを受けて、環境対策の一環として資金を確保するため、ESG債を発行する企業や自治体等が増えてきており、ESG債を購入することで発行元のホームページ等で取り上げられることもございます。
・今年度におけるESG債の購入実績には、日本高速道路保有・債務返済機構などが発行する債券を購入し、合計金額は20億円となっている。
・来年度以降について、安全性や流動性、効率性を考慮しながら、自治体の発行する債券を含めESG債の購入について積極的に検討していく。
◎スポーツ施設の整備について
実現!進行中
課題
私のところに「世田谷区内のスポーツ施設がなかなか取れない、また保護者の方からは、子どものサッカークラブの毎週決まった練習の場所がほしい、なかなか取れない。」とのご意見をいただく。
課題解決に向けた質問・提案1
・私の第1の希望は、世田谷区で新規のスポーツ施設を整備していただきたいということ。
・第2の希望は、とはいえ都市部は地価が高いので、公共の土地だけでは限界があることも認識をしている。
・よって、まずは公共施設の確保、難しい場合には、民間事業者とも連携をして、スポーツ施設の場の確保について工夫をしていただきたい。区の見解を
伺う。
成果
・現在、新たなスポーツの場として、上用賀公園拡張用地や和田堀給水所の上部利用、大蔵運動場及び大蔵第二運動場の整備などについて、計画、検討を進めているところ。
・また、民間事業者との連携は、従来のリコー砧総合運動場のテニスコートに加え、今年の1月からは、給田の第一生命グラウンド内に野球やフットサルができる多目的グラウンド、J&Sフィールドをオープンし、この11月からは同じ第一生命グラウンド内にあるテニスコートについても協議が整い、一部の利用枠を新たに区民利用枠として開放する予定。
・90万を超える人口に対し、区民の方々が気軽に利用できるスポーツ施設がまだまだ十分とは言えないが、引き続き様々な機会を捉え、民間事業者などとも連携し、区民の方が利用できる新たなスポーツの場の確保に努める。
課題解決に向けた質問・提案2
・新規の公共のスポーツ施設としては、上用賀公園内に新規でスポーツ施設の整備が決まっている。
・地元の方からは、「スポーツ施設ができるのはありがたい、また、その他に複合施設として地元の人が集まれる集会室、会議室を整備してほしい。」との声がある。
・この意見を反映しつつ、上用賀公園内へのスポーツ施設の整備について、進捗状況も踏まえて見解を伺う。
成果
・上用賀公園の拡張整備につきましては、令和2年3月に基本構想を策定し、施設整備における基本方針や考え方を示してある。
・この中の体育館の考え方の一つとして、区民大会が開催可能なアリーナやランニングコース、トレーニング室、スタジオ、会議室など、障害者スポーツを含めた多様なスポーツに対応できることを挙げており、これまでの区のスポーツ施設の会議室利用状況や現在行っているワークショップ、近隣住民からの御意見なども踏まえ、会議室については集会室機能など、多目的に利用できるよう検討している。
・今後、基本計画の策定には、施設整備における基本方針を踏まえ、スポーツだけでなく、地域での交流や活動の場など、幅広く活用していただき、地域の方にとって親しみの湧くような施設となるよう進めていく。
◎株式会社ジモティーとの協働事業、不用品再利用実証事業について
課題
区民の方から、次の声をいただきました。「いらなくなった新品同様のキャリーケースを捨てる場合、粗大ゴミに出さなければならない。もったいない・・・誰か使ってもらえれば良いのに。」
課題解決に向けた質問・提案1
・世田谷区は、粗大ごみのリユースを促進するための実証実験を株式会社ジモティーとの協働により令和3年度より実施しており、区民の方に大好評。
・この好評の背景には、近年の粗大ごみの激増により、区の粗大ごみ回収の予約が取りづらくなっていること、また、区の回収に当たっては、あらかじめ粗大ごみの大きさに応じた有料シールをコンビニで購入する必要があるのに対し、実証実験では費用がかからないことがある。
・この事業はあくまでリユースが目的である。
・そこで、これまでの実証実験を通じてどれぐらいの量が持ち込まれ、そのうちリユース品として再利用されたものがどれぐらいあるかなど、区としての当事業への評価を伺う。
成果
・実証実験の実績は、令和3年度から後半の半年で、搬入点数12854点、リユース数12206点で、リユース率は95%、粗大ごみの減量効果は約68、3t。
・令和4年度は4月から8月までの5か月で、搬入点数が14717点、リユース数13424点で、リユース率は91、2%、粗大ごみ減量効果は約68、1tと増加傾向になっている。
・実証実験の途中だが、リユース品の持ち込み数、リユース数とも当初の想定を大きく上回るものとなっており、また手軽に利用できることなどから、粗大ごみ減量の効果だけでなく、区民の皆様に廃棄以外の選択肢が増え、物を大事に使う意識の醸成とリユース行動の促進が図られているものと考える。
課題解決に向けた質問・提案2
・環境省は2022年度、家庭などで使われなくなった衣類や家具などの再利用に関する実証事業を実施すると発表した。
・オンラインショッピングやフリーマーケットアプリが普及したのを受け、自治体による新たな取組を支援するため、自治体からの提案を7月8日まで募集した。採択された事業には最大400万円を助成するとのこと。
・世田谷区の取組は、まさに国の先を行っていたもので高く評価するに値すると思うが、この事業の経費はいくらか、また国の事業への応募をしなかったのか伺う。
成果
・世田谷区の実証実験は、環境省も視察に訪れていたことから、世田谷区も本公募に申請すべく、環境省へ直接協議を行ってきた。しかし最終的に候補日より先行して実施している本実証実験は対象にすることができないとの回答で、申請を行うことはできなかった。
・本実証実験の経費は、令和3年度は協働事業者が全額負担の上で実施、令和4年度は事業費約4000万円のうち、人件費の半額相当と施設賃借料約1600万円を区が負担している。
・本実証実験におけるリユースの売上げに関しては、協定の中に協働事業者に利益が生じた場合は、収支差額を区に還付させることを条項に盛り込み、協働事業者の実証実験運営経費に充当している。
◎新公会計制度について
実現!
課題
・何度か質問・提案した。
・世田谷区の新公会計制度は、洗練されている。
課題解決に向けた質問・提案
・総務省は、このたび全国の地方自治体における新公会計の活用実態について公表した。
・それによると、これまで20年度決算の財務諸表では、全国の91.6%が作成をし、固定資産台帳を整備した自治体は94.1%に上る。ところが、新公会計制度により作成した財務諸表の活用状況では、公共施設等総合管理計画や個別施設計画の策定に活用した自治体は22.8%、公共施設の適正管理に活用した自治体はたったの3.4%だった。
・そこで、総務省では、新公会計制度をより活用するために今後の地方公会計の在り方に関する研究会を立ち上げ、全国の自治体の先進事例を集めて横展開するとのこと。
・私は、世田谷区の取組を全国にPRして広げるべきだと何度か要望している。
・このたび総務省が立ち上げた研究会に参加をし、世田谷区の全国一の先進的な取組を紹介すべきと考える。見解を伺う。
成果
・新公会計制度は、地方公共団体における毎年度の財務書類の作成状況が9割を超え、一定の定着が図られてきた。
・公会計情報の活用や基準の検証など課題があることから、国は学識経験者や都などの自治体、事業者等で構成する研究会を発足させ、8月に第1回目の会議を開催し、令和5年度中を目途に検討を進めることとしている。
・研究会は、世田谷区の公会計制度に係る研修の実施に協力していただいている事業者も委員として参加しており、情報共有していきたい。
・研究会で自治体の取組事例を収集する際は、内部取引による相殺消去の内訳表の公表など、区の取組について情報提供するなど、今後も情報発信に努めていく。
◎不妊治療について
実現!
課題
・不妊治療は、高額な費用がかかるだけではなく、治療を受けている女性の身体的な負担が大きいこと、治療は直前に決まることも多いため、働く女性にとっては仕事の調整も大変なこともあり、仕事との両立が難しく、休職をされたり、中には退職される方もいる。
課題解決に向けた質問・提案1
・既に東京都をはじめ仙台市や鳥取市、熊本市など10近くの自治体が不妊治療休暇制度を設けている。世田谷区でも導入すべきである。見解を伺う。
成果
・区では、国が不妊治療に対する支援に動き出していたことを踏まえ、その動向を注視していたが、本年1月1日より、国家公務員に不妊治療のための休暇制度が導入された。
・区としても、本議会に条例改正案を提案し、先般可決された。
・休暇制度の内容については、日数は一般的な診療時間や日数を踏まえ、5日が付与され、生殖補助医療を行うといった頻繁な通院を要する場合には、さらに5日が加算される。また、会計年度任用職員も含め、有給での対応となる。
・この休暇制度が有効に活用されるよう、管理監督職の理解促進、職員への周知を進めていく。
課題解決に向けた質問・提案2
・今年の4月からは人工受精などの不妊治療が公的保険の適用となる。
・区民の方を対象とした助成制度についても、昨年質問した。そのときの答弁は、国の制度は拡充されたものの、治療を受ける区民の負担は依然重いため、検討を進めていく、とのことだったが、その後の検討状況を伺う。
成果
・特定不妊治療については、高額で経済的負担が重いため、国と都が助成制度を設けており、それらの助成制度拡充に合わせ、区は国と都の助成を受けた区民に対して上乗せ助成を継続してきた。
・令和4年4月1日以降、新たに開始する特定不妊治療については保険診療の適用となる予定だが、令和3年度以前に治療を開始し、年度をまたいで継続する治療は保険適用外となることから、今般、国と都は移行期の経過措置として助成を適用する案を示している。
・区は、移行期の経過措置につきましても、現行の上乗せ助成を行い、区民の不妊治療の経済的負担軽減に取り組む予定。
◎インボイス制度について
課題
・2023年10月1日より、いよいよ我が国の消費税も、帳簿方式から世界標準であるインボイス方式に移行する。
・インボイス方式は、税法上は適格請求書方式と呼ばれているが、適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られ、この適格請求書発行事業者になるためには、適格請求書発行事業者登録申請書を提出し、登録を受ける必要がある。
・この手続きは昨年10月1日から開始されたが、次の4点に注意が必要。
(1)現在課税事業者であっても、この申請登録手続きが必要。
(2)簡易課税事業者の場合、仕入れ先から受け取った適格請求書を仕入れ税額控除のために使用することはないが、自社が適格請求書を発行するためには、この申請登録手続が必要。
(3)現在、課税売上げ1000万円以下の事業者で、免税事業者である場合については、適格請求書を発行するためには、課税事業者選択届だけでは不十分であり、適格請求書発行事業者登録申請書を提出し、登録を受けることが必要。
(4)新制度開始初日から適格請求書を発行するためには、半年前の2023年3月31日までに所轄の税務署に申請書の提出が必要。
課題解決に向けた質問・提案1
・インボイス制度の導入によって、これまで年間売上げが1000万円以下の免税事業者は、引き続き免税事業者のままでいるのか、課税事業者になって消費税の納税義務を負うのかを選択する必要が出てくる。
・今までどおり免税事業者のままでいると、仕入れにかかる消費税を控除するためのインボイスが発行できないため、取引先が仕入れ額控除ができなくなり、取引から外れる可能性があり、免税事業者の中小企業にとっては大きな痛手となる。
・コロナ禍、世間の注目を集めることは少ないが、これは重要な制度改革であり、事業者にとっては非常にインパクトが大きい制度改革。区としても区内の法人や個人事業主に対して情報を提供し、注意喚起する必要があると考えられるが、今後どのような広報をしていくのか、伺う。
成果
・インボイス制度については、産業振興公社による経営支援セミナー「導入で何が変わる?インボイス制度」が、区内の中小事業者や創業予定の方を対象に、本年2月17日に開催されました。このセミナー開催に当たり、「区のおしらせ」2月1日号で周知した。
・今後も、制度内容の理解を深めてもらえるよう、関係所管とも共有し、「区のおしらせ」をはじめとした様々な広報媒体において適切に広報し、周知を行っていく。
課題解決に向けた質問・提案2
・一方で、区役所にとっても多大な影響が生じる。
・現在、消費税法第60条第6項により、区役所は売上げにかかる消費税と同額を仕入れに係る消費税額として控除されるため、消費税を納める必要がない。しかし、来年10月からは、事業者や区民が区に払う公共施設や運動施設、美術館などの入場料や使用料、駐車料金、公有財産の売却や貸付けなど、法律によって消費税が非課税とされている以外の収入に対して、求められれば、税額が明示されたインボイスを発行する必要が生じる。
・また、インボイスを発行するためには、会計ごとに税務署に申請して登録事業者になることが必要。
・さらに、仮に国民健康保険事業会計などの特別会計に、先ほど申した課税対象収入があれば、世田谷区も新たに消費税の課税事業者となる。場合によっては、インボイス制度に対応したレジの導入や新たなシステムの導入が必要となる可能性がある。
・世田谷区の準備状況について伺う。
成果
・区としても、インボイス、適格請求書の発行や、発行事業所としての登録手続、また、新たな財政負担が生じる可能性など、制度の導入により様々な対応が必要となることが考えられる。
・まずは区における影響の全体像を把握し、庁内の役割分担を含め、今後、準備を進めていく。
課題解決に向けた質問・提案3
区として、来年導入されるインボイス制度に関する中小企業への制度の理解推進など、中小企業支援を行っていただきたいと考える。見解を伺う。
成果
課税事業者または免税事業者のどちらを選ぶにしても、現在、免税事業者である中小企業には大きな影響がある。
・中小企業が制度の正確な理解の下にどちらを選ぶかということが的確に選択できるように支援していく必要があると認識している。
・本年2月に産業振興公社でインボイス制度のセミナーを行ったが、例えば、事業者との取引が多い建設業と消費者との取引が多い小売業とでは、受ける影響が全然異なるので、きめ細やかな制度説明会や情報発信などを産業振興公社と連携して行っていく。
◎古着の回収について
課題
区民の方から次のようなご意見をいただいた。
「現在、町会で古着を回収しているが、年に2回と少ない。コロナで中止になり、ますます古着を出す機会がなくなった。家に置いておくのが限界、世田谷区として取り組んでほしい。」
課題解決に向けた質問・提案1
・現在、町会で古着回収を年に2回行っており、良い取組である。
・また、常時持ち込み拠点として、用賀エコプラザとリサイクル千歳台がある。
・しかし、古着回収は、年に2回という欠点もあり、また、コロナ禍で中止も相次ぎ、拠点も少ない状況。
・衣替えのときまで置いておかなければならない、回数を増やしてほしいという声もあることから、回数を増やす工夫をしていただきたい。見解を伺う。
成果
・地区の回収回数等は各団体の事情により異なるが、現在、感染予防策を徹底しながら、各地区での回収が再開されてきた。
・古着回収の機会を増やす方策として、近隣の地区回収の利用できるよう、引き続き区ホームページで区内の回収情報の周知を行うなど、良質なリサイクルにつながる地区回収の利用促進に努めていく。
課題解決に向けた質問・提案2
古着の回収も含め、リサイクルの推進の必要性について、世田谷区の考えを伺う。
成果
・リサイクルを推進することで資源の有効活用を図ることが可能となる。
・しかし、リサイクルも環境負荷を生じ、ごみとして処理する以上の費用がかかることもある。
・よって、区では、不要なものを発生させない取組として、2Rである発生抑制、リデュース、それと再使用、リユースを推進している。
・本区としては、2Rの取組をしてもなお発生した不要なものについては、環境負荷の少ない最適なリサイクル手法によって資源の有効活用を図っていく。
◎妊活支援について
実現!
課題
妊活による身体、精神的、経済的な負担が大きいという声をいただく。
課題解決に向けた質問・提案
・このテーマは以前に質問した。
・妊活から妊娠、出産、育児まで包括支援体制を考える自治体が増えてきており、妊活による身体、精神的、経済的な負担の大きさを考慮して、一刻も早い相談しやすい環境を整えること、そして望んだときに妊娠、出産ができるような環境を整えることが急務である。
・例えば横須賀市では、この妊活の相談体制を構築するためにLINEを活用した専門性を備えた民間企業の妊活サポートサービスを導入しており、世田谷区も横須賀市の事例を参考にし、官民連携で区民の方に妊活支援を行っていただきたい。
・その後の進捗状況と今後について伺う。
成果
・横須賀市は、全国に先駆けてLINEを活用した妊活相談サービスを民間事業者と連携して開始したが、その後、令和3年度に杉並区が同様のサービスを開始したことを区は把握し、この間、情報収集を重ねてきた。
・妊娠を希望する区民にとってLINEによる専門的な相談を匿名で受けることができる民間事業者による相談サービスは、区へ直接相談するよりも敷居が低く、利用しやすいと認識している。
・こうした利用しやすい相談体制の整備が強く求められている一方で、個人情報保護の面では課題も残されていることから、妊娠を希望する区民が安心して気軽に相談できる体制整備に向けて、慎重に検討を進めていく。
◎自然生態系の保全について
課題
・昨年、世田谷区内の養蜂場を見てきた。その際、次のような深刻な状況を伺った。
・「蜂の活動期は春から夏にかけてで、そのときに蜜を花から運んで冬に備えるとのこと、この蜂が存続していくためには、蜂だけでは完結せず、周りの環境がとても大切。しかし、現在、都内にある花壇や花などが減り、ミツバチの生育できる環境が少なくなってきてしまっている。また、相続などで周りのお屋敷がなくなってしまい、緑が減ると、花や木もなくなってしまい、蜂もいなくなり、滅びてしまう危険性がある。」
課題解決に向けた質問・提案1
・私は、人間は自然の生態系の中で生かされており、自然と共存しているのだと改めて気づいた。
・人間が生きる地球の自然環境は、虫たちがいなければ成り立たず、中でもミツバチは植物の花粉交配をし、緑を増やす役割を担っている。ミツバチが生きられる環境を保全することは、人間が生きられる環境の保全と言える。
・今年の調査で、みどり率の減少という結果になったが、緑は生物多様性を支える重要な土台であり、緑の減少は生物多様性の危機に直結する。
・まず、生物多様性の保全の重要性について、区の見解を伺う。
成果
・私たちは、食料や水、気候の安定など生活の気づかないうちに大変多くの生物多様性の恵みを受けており、その恵みは生き物の生息、生息地の提供、資源の供給、生活環境の調整、豊かな暮らしと文化の創造の4つに分けられる。
・生物多様性は人が暮らしていく上で必要不可欠なものであり、生き物とともにある暮らしと緑豊かな環境を次代に引き継ぐため、区では平成29年に生物多様性地域戦略として、生きものつながるプランを策定した。
・区ではプランに基づき、生き物が豊富な国分寺崖線を起点として、植物や鳥、昆虫が区内に広がっていけるよう、国分寺崖線の緑の保全、大規模な公園などの緑の拠点の整備、町なかの小さな緑である宅地や公共施設の緑化など、緑の取組により、緑道や河川などと併せた生き物のネットワークづくりを取り組んでいく。
課題解決に向けた質問・提案2
・特に世田谷区のような都市部において、生物多様性の価値はなかなか実感しくいものだと考える。
・緑を創出し、生物多様性を保全していくためには、その価値を実感できるよう区民の方が暮らしの中で生物多様性を身近に感じられるような環境づくりが必要。
・区民の方が身近に生物に触れる環境づくりや、区民の方の関心を高めるための区の取組について伺う。
成果
・区では、身近な町の中に生き物の生息環境を広げるため、ひとつぼみどりの創出として、生き物を呼ぶ緑づくりを区民に提案し、花壇づくりなどの助成制度や、花いっぱい協定制度などの活用などの取組を進めている。
・桜丘すみれば自然庭園では、ボランティアを中心とした生物多様な環境づくりを行うなど、区民が身近に生物多様性を感じられる場づくりに取り組んでいる。
・区民の関心を高める取組につきましては、まちの生きものしらべとして、区民参加の生物調査を行っており、今年度の調査では3015件の報告を受けた。
・自分の身の回りの生き物を調べることで、生き物にとって住みやすい町の環境をどうやってつくったらいいのか考えるきっかけになっている。さらに、緑や生物多様性の大切さを子どもたちに伝えることを目的として、小学校を対象に、みどりの出前講座を実施している。
・今後とも、環境教育として学校へのアプローチや区民が参加しやすい事業の実施、ホームページや広報物などによる身近な生物の紹介など、区民が生物多様性を実感し、関心を高めていけるように取組を進めていく。
議会中継動画
定例会名
- 令和5年第2回定例会 一般質問
- 令和5年第1回定例会 予算委員会
- 令和5年第1回定例会 一般質問
- 令和4年第4回定例会 一般質問
- 令和4年第3回定例会 決算委員会
- 令和4年第3回定例会 一般質問
- 令和4年第2回定例会 一般質問
- 令和4年第1回定例会 予算委員会
- 令和4年第1回定例会 一般質問
- 令和3年第4回定例会 一般質問
- 令和3年第3回定例会 決算委員会
- 令和3年第3回定例会 一般質問
- 令和3年第2回定例会 一般質問
- 令和3年第1回定例会 予算委員会
- 令和2年第4回定例会 一般質問
- 令和2年第3回定例会 決算委員会
- 令和2年第3回定例会 一般質問
- 令和2年第2回定例会 一般質問
- 令和2年第1回定例会 予算委員会
- 令和2年第1回定例会 一般質問
- 令和元年第4回定例会 一般質問
- 令和元年第3回定例会 決算委員会
- 令和元年第2回定例会 一般質問
- 平成31年第1回定例会 予算委員会
- 平成31年第1回定例会 一般質問
- 平成30年第4回定例会 一般質問
- 平成30年第3回定例会 決算委員会
- 平成30年第3回定例会 一般質問
- 平成30年第2回定例会 一般質問
- 平成30年第1回定例会 予算委員会
- 平成30年第1回定例会 一般質問
- 平成29年第4回定例会 一般質問
- 平成29年第3回定例会 決算委員会
- 平成29年第3回定例会 一般質問
- 平成29年第2回定例会 一般質問
- 平成29年第1回定例会 予算委員会
- 平成29年第1回定例会 一般質問
- 平成28年第4回定例会 一般質問
- 平成28年第3回定例会 決算委員会
- 平成28年第3回定例会 一般質問
- 平成28年第2回定例会 一般質問
- 平成28年第1回定例会 予算委員会
- 平成28年第1回定例会 一般質問
- 平成27年第4回定例会 一般質問
- 平成27年第3回定例会 決算委員会
- 平成27年第3回定例会 一般質問
- 平成27年第2回定例会 一般質問
- 平成27年第1回定例会 予算委員会
- 平成27年第1回定例会 一般質問
- 平成26年第4回定例会 一般質問
- 平成26年第3回定例会 決算委員会
- 平成26年第3回定例会 一般質問
- 平成26年第2回定例会 一般質問
- 平成26年第1回定例会 予算委員会
- 平成26年第1回定例会 一般質問
- 平成25年第4回定例会 一般質問
- 平成25年第3回定例会 決算委員会
- 平成25年第3回定例会 一般質問
- 平成25年第2回定例会 一般質問
- 平成25年第1回定例会 予算特別委員会
- 平成25年第1回定例会 一般質問
- 平成24年第4回定例会 一般質問
- 平成24年第3回定例会 決算特別委員会
- 平成24年第2回定例会 一般質問
- 平成24年第1回定例会 予算特別委員会

